第32回 クリエイティブ・サロンのご案内(7月5日)
- 主催 学術研究団体 日本創造学会
- 開催日 2014年7月5日(土)
- 会場 日本経済大学大学院1階246ホール (文末地図参照)
- 住所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町25-17
- 参加費 会員/無 料 非会員/資料代として500円 ※懇親会(希望者)は3500円 程度の実費
- 参加の際、筆記用具をお持ちください
- 研究会講師
英 真一氏【第1部 講演会】「人が見えてるのになぜ写真には写らないか~の謎を説く」~『画像』その役割と発想~
澤泉重一氏【第2部 ワー クショップ】「"偶然の発見"を体験しよう」実践!セレンディピティの活用 ~偶然を活かすメソドロジー~ - スケジュール
12:30 開 場
13:00-14:30 第1部 講演会
14:30-15:00 休憩・開場整備
15:00-18:00 第2部 講演会&ワークショップ
18:15~ 別会場にて懇親会
【第1部 講演会】「人が見えてるのになぜ写真には写らないか~の謎を説く」~『画像』その役割と発想~
|
【講師プロフィール】
英 真一 1989年~2006年 コニカミノルタ株式会社、2007年 SERENDIPITY株式会社設立、2009年~2011年 富士フィルム株式会社、 2011年 MAM株式会社設立。現在、SERENDIPITY株式会社代表取締役、株式会社ラボネットワーク技術顧問 (講演会概要) 近年、飛躍的な発達を遂げたデジタル画像、従来のアナログ写真を引き継ぐ画像の画創りとセンサー技術が基礎特性を全域で 駆使することで取り出せる様々なデジタル画像の役割を画像例をご紹介しながら進めてまいります。 “人が見えているのになぜ写真には写らないのか”という永遠の疑問から、デジタル画像は“人間が判断できる画像を表現する” という目的に向かい現在はどのような地点に立っているのか。人の目とセンサー技術を通し画像とその意義をお話ししたいと思います。 社名となっておりますSERENDIPITYですが、発想の根源は多くのカオスから成り立つという原理に基づいております。 事象や現象の多くは膨大に蓄えられたデータから特定されるものであり、 近年優秀な成果を上げつつあるビッグデータはまさにSERENDIPITYの集大成といえるでしょう。 |

|
【第2部 ワークショップ】「"偶然の発見"を体験しよう」実践!セレンディピティの活用 ~偶然を活かすメソドロジー~
|
【講師プロフィール】
澤泉 重一 電機メーカで海外プラント建設に従事。体験した偶然の活用法を研究。富山県立大学大学院MOTコースで 「創造性開発研究(Creativity and Serendipity)」を講義。 受講生が立ち上げた企業向けセレンディピティ活用研究会開催。偶発的発見セレンディピティの研究で京都大学情報学博士取得。 著書に『偶然からモノを見つけ出す能力』(角川Oneテーマ21, 2002)、『セレンディピティの探究』(共著、角川学芸出版、2007), 『知の協創支援』(共著、オーム社、2010)。日本創造学会会員、SAM(Society for Advancement of Management) Director (講演会&ワー クショップ概要) 思いがけないものを発見する才能"セレンディピティ"は、誰もが有している能力ですが、その活用の度合いは個人々々によって 大きな違いが見られます。才能を眠らせたままで、これを活かせていない人が多いように見受けられます。 本ワークショップでは、偶然の作用と偶発的発見のメカニズムを解説するとともに、 日常生活にセレンディピティ発揮のトレーニングを組み込む方法を紹介してその一部を試行し、質疑応答を行います。 1st Step : 実施例の紹介 2nd Step :単純化した偶発的発見モデルの紹介 a. 発見:偶然、察知、アブダクション、仮説 b. 有効なS’ty仮説:情報価値、外化、仮説立案の試行 3rd Step : 情報収集(セレンディピティ・カード)、 a.カードの特長:保管、加工、ブレイン・インベントリー b.関係性の発見:発散過程から収束過程へ、Foresight Card、意義付け 4th Step : 各チーム発表と質疑応答 (了) |

|
参加を希望される方は、事務局 比嘉(jcs-info@japancreativity.jp)まで以下をメールでお申込みください。
--- ここから ---
氏名:
所属:
会員:○ or × (どちらかをご選択ください)
懇親会参加:○ or × (どちらかをご選択ください)
--- ここまで ---
会場の地図

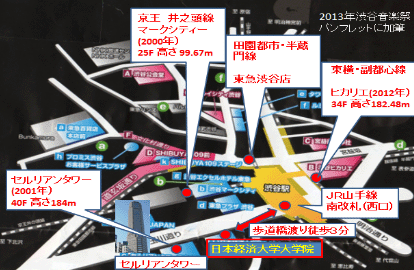
次回(33回)クリエイティブサロンの予告
次回は、9月13日(土)午後に開催予定です。詳細は、学会メールでのお知らせ・学会ホームページ・学会Facebookページなどで追ってお知らせいたします。




